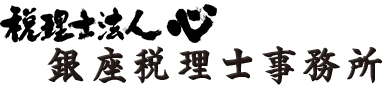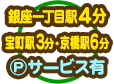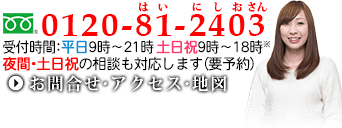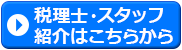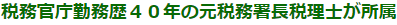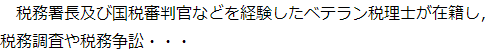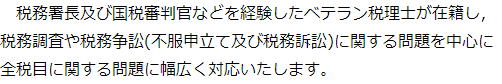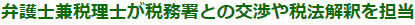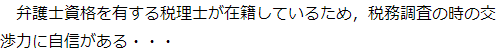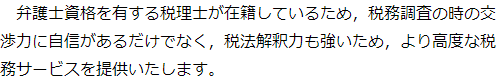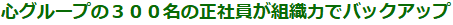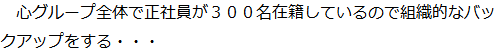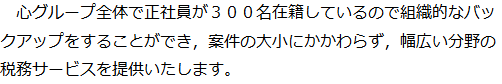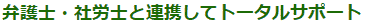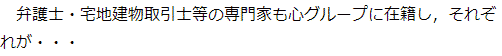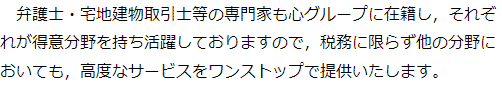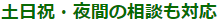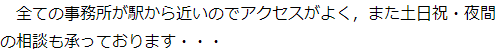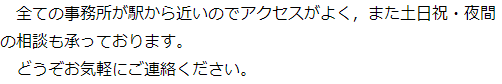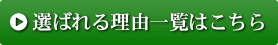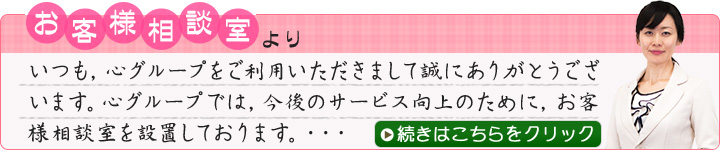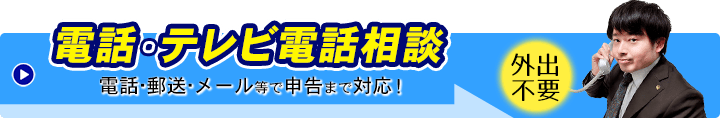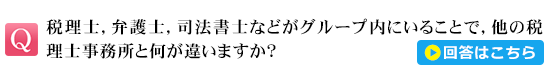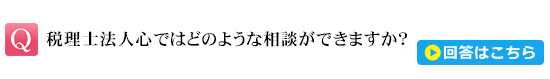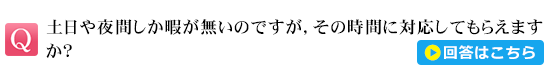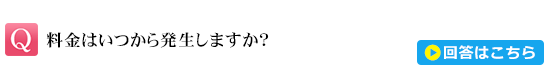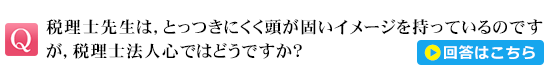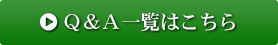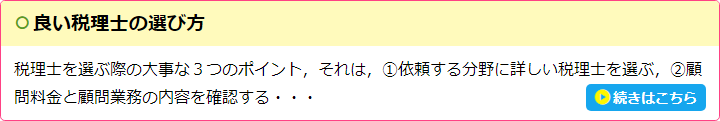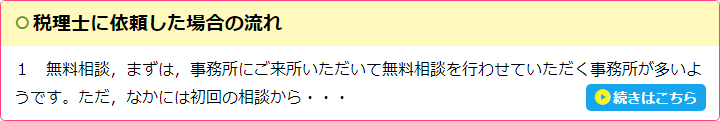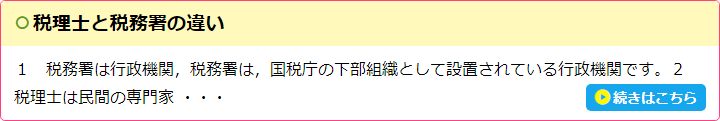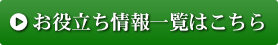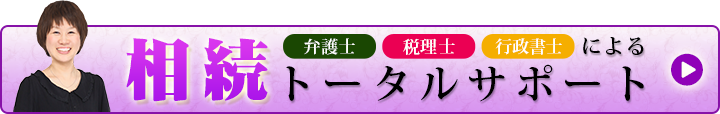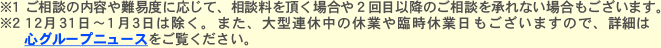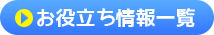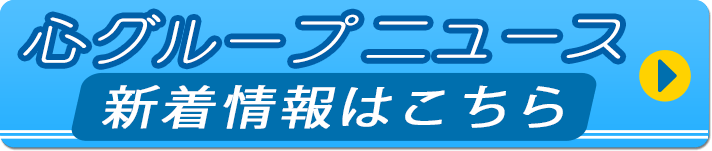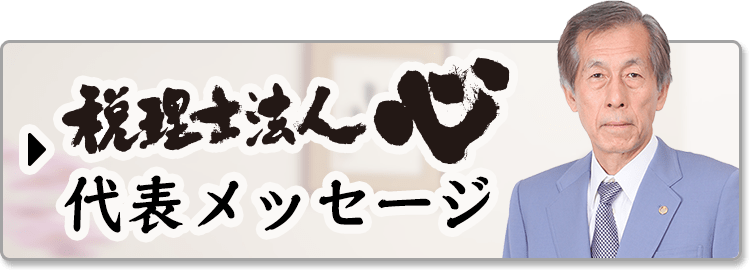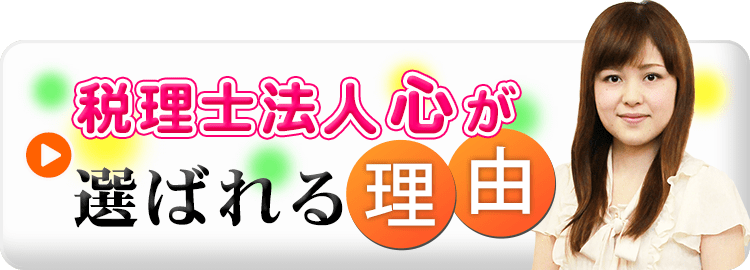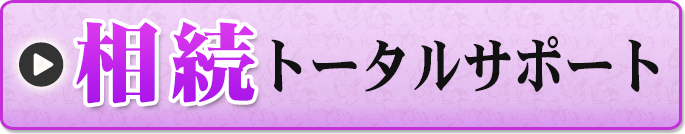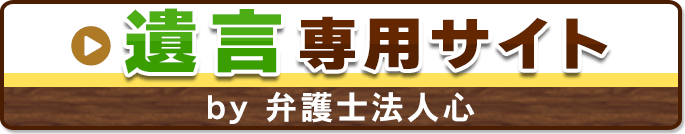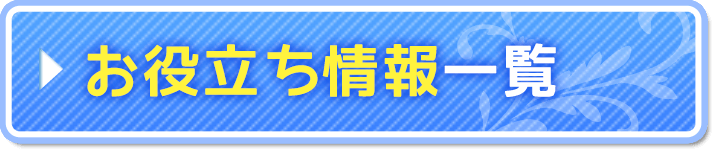駅の近くにある事務所です
当法人の事務所はどれも最寄り駅から徒歩圏内の場所にあります。銀座にも事務所があり、所在地や詳しい地図はこちらから確認できます。
税理士に相談するとよいケース
1 事業を始める場合

個人事業を始める際や、個人事業主が法人化を検討する際には、税理士に相談することをオススメします。
これは、事業をはじめたばかりのときでなければ、利用することのできないような節税制度もあるからです。
例えば、小規模企業共済は、建設業、製造業、運輸業、不動産業等の場合は、常時使用する従業員数が20人以下の場合、小売業や宿泊業・娯楽行以外のサービス業や弁護士・税理士などの士業法人の場合は常時使用する従業員の数が5人以下でなければ、加入することができません。
このような加入した方がよい制度へのアドバイスをもらえますので、税理士に相談するとよいでしょう。
2 一般口座での株取引がある場合
特定口座で株式の売買や配当を受けている場合は、証券会社の方で源泉徴収をされます。
ですので、あえて確定申告をすることで税金を安くしたいという方以外は、特に確定申告を行わなくとも問題はありません。
これに対し、一般口座での株取引がある場合は、確定申告を行う必要があります。
取引履歴等を見ながら、ご自身で確定申告を行うことができる方はご自身で申告されても構いませんが、自身のない方は税理士に相談しましょう。
3 相続税の節税対策を行いたい場合
相続税や贈与税は、法改正によって110万円ずつの生前贈与を活用しづらくなるなど、増税の方向への法改正が行われている税目ですので、適切な相続税対策を行うためには、税理士に相談することをオススメします。
4 税務調査の連絡を受けた場合
税務調査では、税務署から質問を受けた際に適切な応答ができなければ、納付する税金を増やす方向での修正申告をするように促されることも多くあります。
そのような指摘を受けた際に、税法、通達、国税不服審判所の審判例、裁判例などに基づき、適切な応答をするためには、税理士に相談し、アドバイスを求めるか、または最初から税務調査に同席してもらうことをオススメします。
税理士に相談するべきタイミング
1 個人事業主の場合

開業前には税理士に相談することをおすすめします。
開業時には、開業届など税務署に提出しなければならない書類や、青色申告承認申請書のように税務署に提出しておけば今後の税金を安くすることができる書類等があります。
また、取引先からインボイスの登録事業者になることを求められているものの、どのようなメリット・デメリットがあるのかよく分からない場合もあるかと思います。
そのような場合、税理士であれば適切なアドバイスをすることができますので、事前にご相談ください。
2 法人成りを検討している場合
会社を設立する前に、税理士に相談することをおすすめします。
個人事業主から法人成りした方が、税金が安くなると思われがちですが、法人化すると、法人税だけでなく、法人住民税や法人事業税などの税金もかかります。
また、社会保険への加入が義務づけられますので、会社の社会保険料の負担は重くなります。
そのため、一概に法人化した方が負担が軽くなるとはいえません。
法人成りを検討している場合は、手続を行う前に税理士に相談されることをおすすめします。
3 相続税対策を検討している場合
相続税対策を検討している場合も、税理士にご相談ください。
特に、相続税対策では、早めに生前贈与をはじめておくことが有効な節税対策の一つでもありますので、できる限り早めに税理士に相談されることをおすすめします。
4 家族が亡くなった場合
ご家族が亡くなると、準確定申告や相続税申告が必要となる可能性があります。
特にこれらの手続きは、準確定申告が亡くなった日の翌日から4か月以内、相続税申告は亡くなった日の翌日から10か月以内と期限が定められておりますので、それまでに手続きを終える必要があります。
これらの期限が過ぎてしまいますと、延滞税や無申告加算税等の税金が加算されてしまうことがありますので、早めに税理士に相談し、スムーズに手続きを行うことができるようにすると安心です。
税理士法人心の特徴
1 税務署長経験者が所属

税理士法人心には、税務署長を経験した国税OBが所属しています。
その経験から、税務調査対応の経験も豊富ですし、税務署側が何を目的として税務調査を行っているのか分析し、対応することを得意としています。
2 得意分野を持っています
当法人では、所得税・法人税・消費税といった企業税務を取り扱う税理士、相続税を取り扱う税理士がいます。
一人の税理士がすべての税目を取り扱うのではなく、それぞれの得意とする分野を持ち、対応しています。
税理士はすべての税目について詳しいと思われがちですが、税理士試験ではすべての科目を選択することはなく、選択科目式ですし、実務に出てからでも普段取り扱わない税目はあまり詳しくないのが現実です。
当法人では、それぞれの税理士が得意とする分野を対応することで、その分野に対する経験数を上げ、専門性を高めることを目指しています。
3 弁護士兼税理士が所属
税理士法人心では、弁護士兼税理士が多数所属しています。
弁護士兼税理士のメリットは、法律・税金の両方に対応することができる点です。
弁護士は、法律には詳しいですが、税金にはあまり詳しくないことが一般的です。
他方で、税理士は、税金には詳しいですが、法律には詳しくないことが一般的です。
ただ、例えば、相続の分野では、相続税を計算するうえで、法定相続分や相続放棄、遺言、遺留分などの法律が理解できていなければ、正確に計算することはできません。
他にも、例えば、会社が従業員に毎月の給与以外の金銭を渡した場合、金銭消費貸借契約書を作成する等しておかなければ、給与とみなされ課税対象となってしまうことがありますが、金銭消費貸借契約は弁護士の分野ですので税理士は作ることができません。
税理士法人心では、弁護士兼税理士が対応しておりますので、法律・税金のどちらにも対応することができる点が特徴といえます。
税理士に相談する際の流れ
1 相談する先の税理士が取り扱っている分野かどうか確認する

税理士と言えば、すべての税務について詳しく何でも相談できると思われがちですが、実際には税理士にもそれぞれ得意分野があります。
特に普段から個人事業主や企業の顧問業務を行っている税理士の場合は、所得税・法人税・消費税については詳しいと思いますが、生前贈与や相続税対策など、相続税の事は普段取り扱いが少ないため、あまり得意ではないこともあります。
そのため、相談する内容を、相談先の税理士が取り扱っているのか、得意としている分野なのかを確認することが大切です。
2 相続税の相談の場合
⑴ 事前の相続税対策のとき
家族構成やご家族の年齢が分かるようにご準備いただき、あらかじめどなたに何の財産を渡したいのか決めている場合は、そちらもメモ書き等していただいたうえで、ご相談くださるとスムーズに話が進められます。
その場合は、現状のご希望をもとにいくらの相続税がかかるかシミュレーションを行い、そのうえで税額が安くなりそうなプランをご提案させていただき、順次、実行していく流れになります。
⑵ 相続税申告のとき
既にご家族が亡くなっている場合は、相続税申告のご相談にのらせていただきます。
相続税申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内が申告期限になりますので、除籍謄本や住民票の除票など、亡くなった日がわかる資料があるとスムーズです。
また、ご家族構成がわかるように相続関係図を書いておいていただいたり、亡くなった方の財産の一覧のメモ書きなどがあると、スムーズに話を進められます。
とくに、相続人の人数によって、相続税の基礎控除額が異なりますので、相続関係図と大まかな財産の一覧があると、相続税申告が必要かどうかの判断もできますので有益です。
3 個人事業主や法人の場合
既に、ご依頼されている税理士がいらっしゃる場合は、現状の税理士の問題点や税理士を変更したい理由などをまとめておいていただき、ご相談にのらせていただくとスムーズです。
顧問税理士がいる・いないにかかわらず、過去3期分の決算書・申告書を拝見させていただくと、現状の把握ができますので、ご相談の際には、ご準備されることをおすすめします。
そのうえで、顧問料などのご提案をさせていただき、双方合意ができればご契約という流れになります。
税理士に依頼した場合の料金はどのように決まるのか
1 税理士報酬の決められ方

平成14年3月までは、税理士法に税理士報酬に関する規定があり、各税理士会が報酬規程を定めていましたが、その後、規程は廃止されました。
そして、現在では、税理士報酬は自由化され、税理士事務所が独自に料金体系を決めることができるようになっています。
報酬体系も自由ですし、報酬額も自由です。
そのため、税理士に依頼した場合の料金は、依頼の内容、業務の複雑さ、専門性、地域などによって異なります。
ここでは、税理士に依頼した場合の料金について、ケース別にいくつか目安を説明していきます。
2 個人又は法人が顧問契約を結ぶ場合
顧問契約を結ぶ場合、顧問料の他に記帳代行料、決算料等がかかります。
また、給与計算及び年末調整については、一人当たりいくら等と、従業員の人数で変わります。
他にも、個人よりも法人のほうが作成すべき申告書類が多かったり、税務処理が複雑になる傾向があるので、税理士報酬も増える傾向にあります。
3 相続税申告を依頼する場合
相続税申告の税理士報酬は、遺産の総額、相続人の人数、土地や非上場株式といった評価を行う必要のある複雑な財産がどの程度あるか、申告期限までどの程度時間が迫っているか等の要素によって、金額が決まります。
相続財産の複雑さにもよりますが、遺産の総額の1%が税理士報酬の目安といわれています。
4 税理士との契約の際のポイント
税理士報酬がいくらなのかというのは、税理士に依頼する際の重要な要素となることもあるでしょうし、複数の税理士事務所から依頼先を選ぶ際の比較検討の材料にもなるかと思います。
しかし、金額の安さだけで決めるのは避けたほうが良いです。
税理士に依頼する際には、その税理士がどの程度の専門性を有しているのかも確認し、どこまでの業務を依頼するのか事前に考えたうえで、見積もりを出してもらうことが重要です。
対応範囲を明確にしておかないと、「この料金でここまでやってもらえると思っていた」等、想定とは違った結果となってしまうおそれがありますので、費用の詳細をしっかりと確認することも大切です。
当法人の税理士費用については、費用のページで目安をご説明していますし、相談の際には税理士から詳細をご説明させていただきますので、ご安心ください。